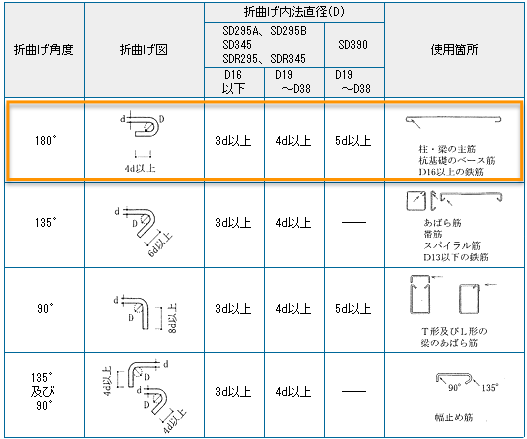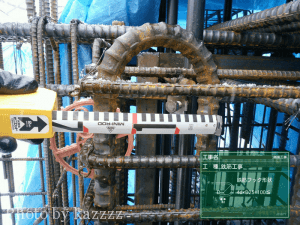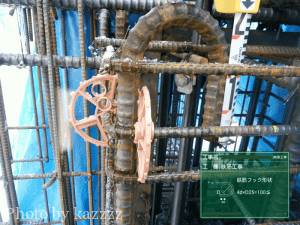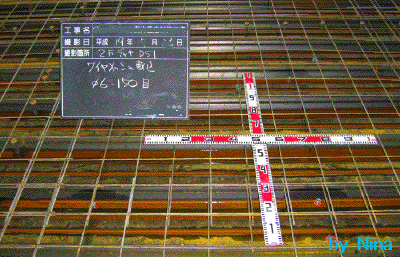久しぶりの、カテゴリー「鉄筋工事」です。
過去記事は、ぜひ「過去に紹介した、鉄筋工事のまとめ記事」を、ご覧ください。
今回は、鉄筋加工にはかかせない「フック」についてです。

この基本がしっかり頭に入っていないと、現場で臨機応変な対応が出来なくなってしまいます。
最初に覚えることは、下表です。
※日本建築学会編「建築工事標準仕様書(JASS5)」による
この表をしっかり頭に入れることによって、すべてがうまくいきます。
折り曲げ加工は、冷間加工とし、折曲げ機を使用するのが基本です。
建築学会の基準では、一般的にD16以下は3d以上、D19以上は4d以上となっています。
したがって、D16であれば、
16×3=48mmが最小直径Rです。
半径では24mmですね。
また、余長=8d(90°の場合)となっているので、
16×8=128mm
合計で、48mm × 円周率π/2 + 128mm = 203.36mm
これが、最小で曲げられる鉄筋の必要な長さとなります。
下の写真は、基礎柱主筋のフック形状です。
折り曲げ加工180°のD25mmです。
(クリック拡大)↓
鉄筋端部のフック取り付け箇所は、下記です。 ※建築基準法施行令第73条による。
- 柱の4隅にある主筋で、重ね継手の場合。及び最上階の柱頭にある場合。
- 梁主筋の重ね継手が、梁の出隅及び下端の両端にある場合。(基礎梁を除く)
- 煙突の鉄筋。
- 杭基礎のベ一ス筋。
- 柱フープ・梁スタ一ラップ及び幅止筋。
加工時に急激に鉄筋を折曲げると、大きな内部応力が発生し、曲げ部分に有害なひび割れが発生する原因となります。
これからも鉄筋加工には、丁寧な仕事が求められることでしょう。
関連記事もご覧ください